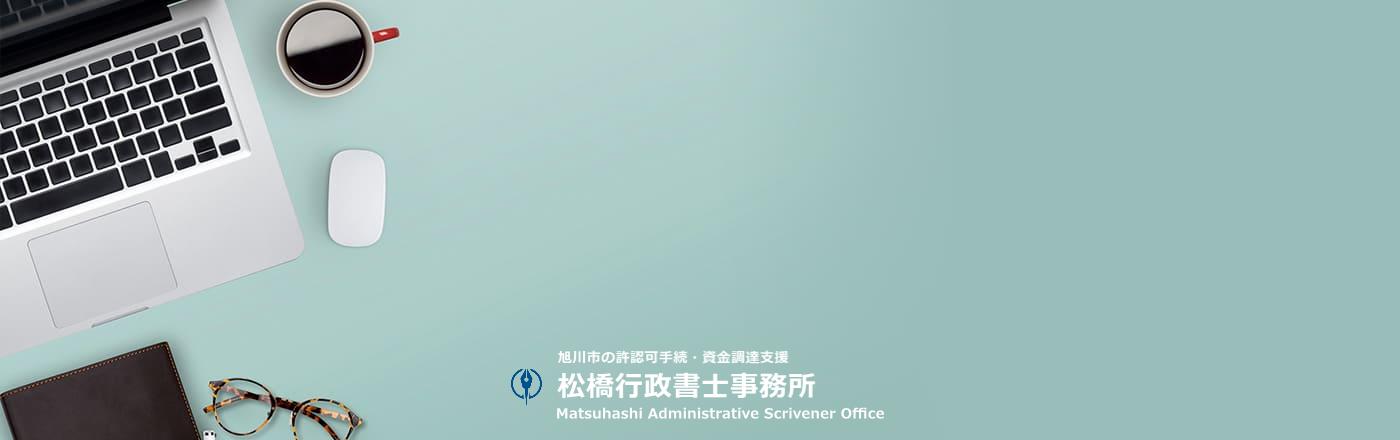
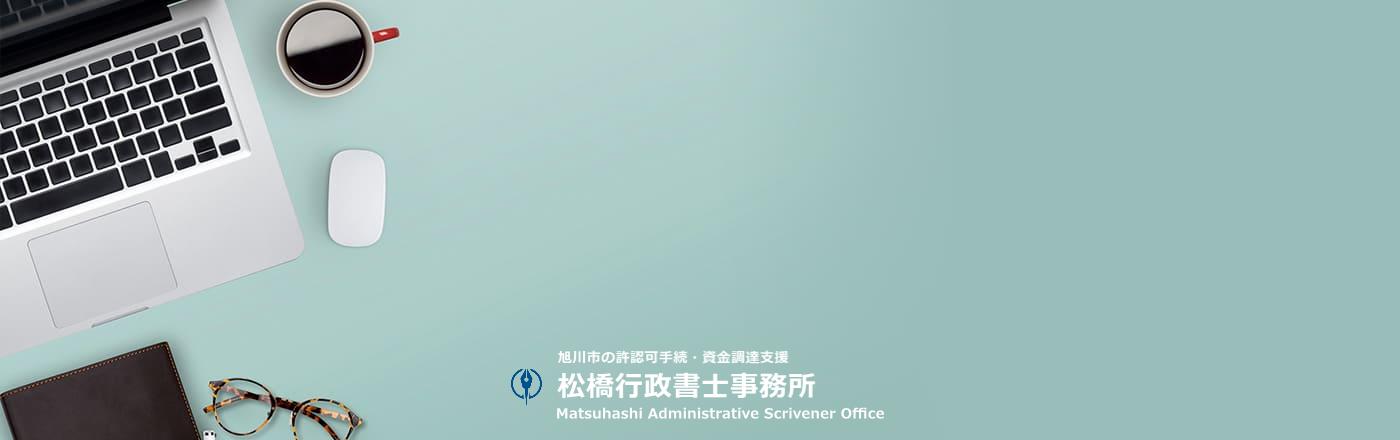
請負契約に関しての誠実性があること
建設業許可における「誠実性」とは、建設業法第7条第3号に定められた許可要件のひとつで、請負契約の締結や履行に関して「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」を意味します。「誠実性」は、一般的な人格的評価や道徳観ではなく、あくまで契約の場面に限定された要件となります。
誠実性が求められる理由
建設業は公共性・公益性が高く、発注者との信頼関係を前提に成り立つ産業です。工事は長期間に及び、前払金や中間金の支払いが発生するため、契約違反や不正があれば発注者に大きな損害を与えることになります。そのため、契約を結ぶ段階や工事を履行する段階で不正・不誠実な行為を行うおそれがある者には許可を与えない仕組みになっているのです。
誠実性の対象者
法人の場合は会社そのもの、取締役・代表取締役などの役員、さらに営業所を統括する「令第3条使用人」(支店長や営業所長など)、個人事業主の場合は本人および支配人(営業所の代表者)です。現場代理人や主任技術者は直接の審査対象ではありませんが、行為が不正にあたれば会社や役員の責任が問われます。
誠実性を欠くとされる典型例
契約時に虚偽の説明をして発注者を誤認させる。
契約内容と異なる仕様で施工する(手抜き工事など)。
架空請求や過大請求、代金の横領。
談合や贈収賄を伴う入札行為。
無許可営業や名義貸し。
契約で定められた工期を正当な理由なく遅延させる。
天災等による損害負担を契約に反して一方的に押し付ける。
誠実性を欠いた場合の影響
建設業許可の新規申請時に誠実性を欠くと判断されれば許可は下りません。また許可取得後に不正が発覚すれば、許可取消処分や営業停止処分の対象となります。
上記をまとめると、建設業許可における「誠実性」とは、請負契約の締結や履行において不正や不誠実な行為を行うおそれがないことを意味し、単なる道徳的な誠実さではなく、法的に限定された要件です。許可を維持するためには、日常業務の中で契約遵守と透明性を徹底し、信頼を損なう行為を未然に防ぐ体制づくりが不可欠となります。