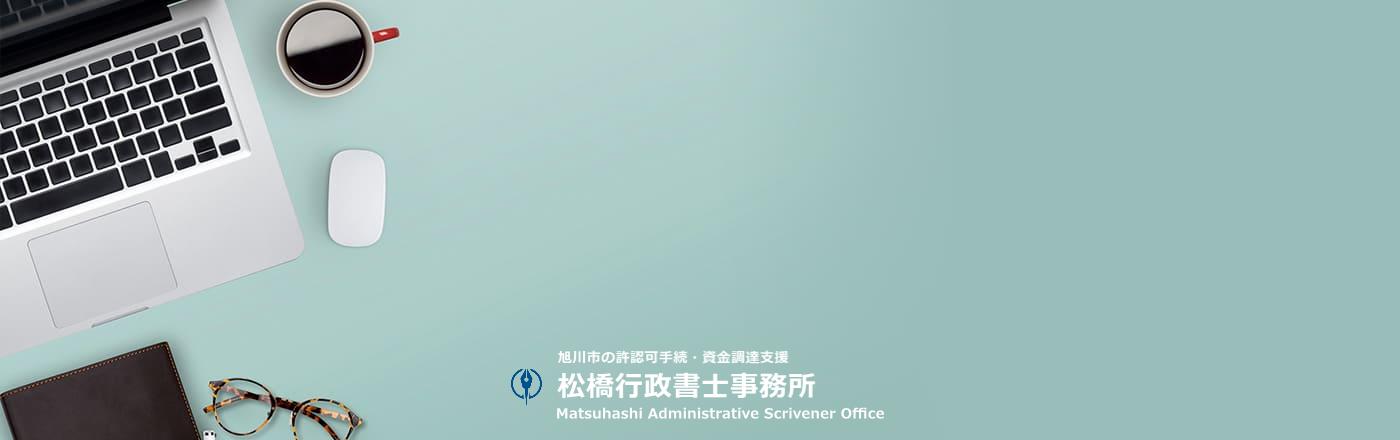
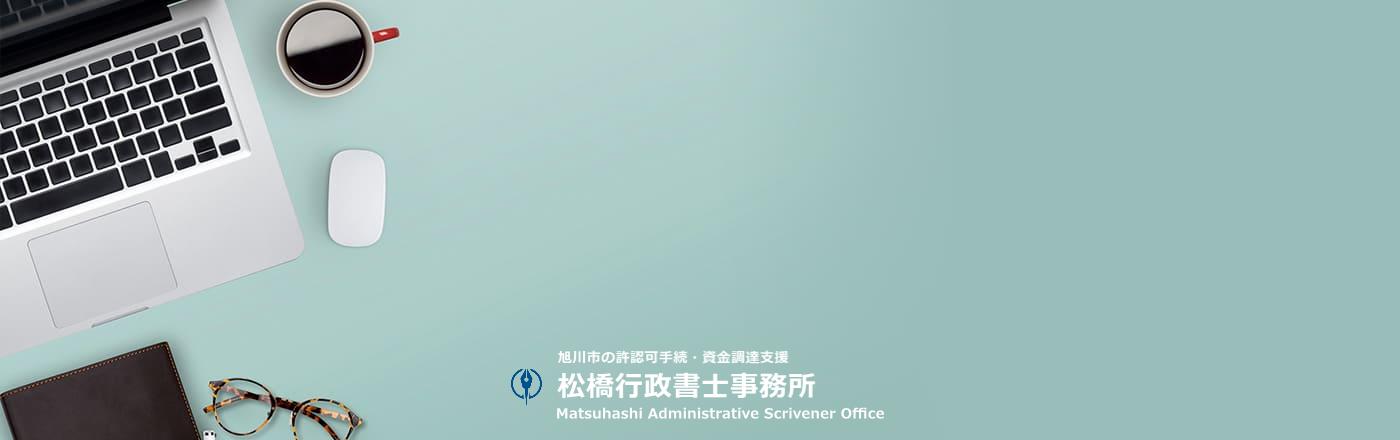
欠格要件に該当していないこと
建設業許可を受けるためには、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当していないことが必須条件となります。事業者や役員の社会的信用や法令遵守の姿勢を確認するための基準です。欠格要件に該当している場合、建設業許可が下りない、あるいは既に持っている許可が取り消されることになります。
対象となる人
欠格要件は、事業主本人だけでなく、法人の場合は代表取締役などの役員、さらに支店長や営業所長といった重要な使用人にも及びます。経営の中枢に関わる人が一人でも該当すると、会社全体が許可を受けられなくなる可能性があります。
主な欠格要件の内容
破産手続開始の決定を受けている場合
破産手続中の人は欠格にあたります。ただし、裁判所から免責許可決定が確定し、復権した場合は欠格状態が解消されます。
禁錮以上の刑を受けた場合
懲役や禁錮刑を受け、その判決が確定した日から5年間は欠格に該当します。執行猶予付きでも同じ扱いです。
建設業法違反で罰金刑を受けた場合
罰金刑の執行を終えてから5年間は欠格に該当します。違反内容によっては許可取消処分も伴うことがあります。
許可取消処分を受けた場合
行政庁から正式に許可を取り消された場合、その日から5年間は新たに許可を受けられません。自主廃業の場合は欠格には当たりませんが、処分逃れと見なされると同様の扱いになることがあります。
成年被後見人または被保佐人
精神上の理由で後見や保佐の審判を受けている場合は申請できません。
暴力団関係者
現在暴力団員である人、または脱退後5年を経過していない人は欠格に該当します。
欠格要件に該当しないことの証明書類等
申請時には自分や役員が欠格要件に当たらないことを証明するために、以下のような書類を提出します。
誓約書(欠格要件に該当しない旨の自己申告)
登記されていないことの証明書(後見・保佐の登記がないことを証明)
身分証明書(破産者や禁治産者でないことの証明)
必要に応じて医師の診断書
上記をまとめると、欠格要件に該当していないこととは事業者や役員が破産中でない、重大な刑罰を受けていない、建設業法違反歴がない、暴力団関係者でないなど、社会的信用を損なう状態にないことを意味します。建設業者としての社会的な信頼性を担保するための重要な基準となります。